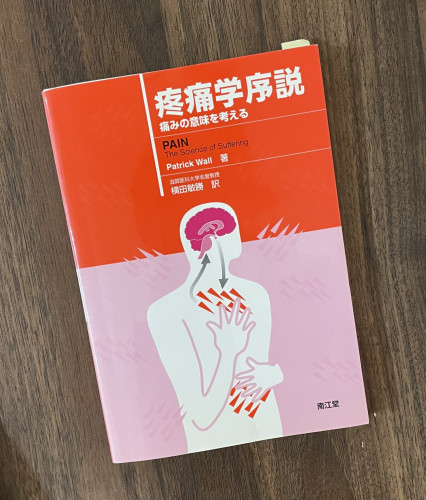そよ風 note
25年前の本に書いてあること
この本は1999年にイギリスで出版された
『PAIN The Science of Suffering(痛み:苦痛の科学)』の日本語版
『疼痛学序説 ー痛みの意味を考えるー』(南江堂 2001年)です。
この本も大阪のセミナーに向かう新幹線の中で読んでいたので、20年ほど前に購入したと思います。
著者のPatrick D. Wall(パトリック・ウォール) は、偉大な神経科学者であり、20世紀最大の疼痛学者の1人である。とこの本でも紹介されています。
パトリック・ウォール(1925 – 2001)は、痛みを科学する人、痛みの専門家です。
痛み治療に携わる人で、知らない人はいないでしょう。
25年前に出版されたこの本には、椎間板ヘルニアもヘルニアに対する手術もすでに疑問視されていることが書かれています。
筋筋膜性疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome)の説明もあります。
その③ 筋筋膜性疼痛症候群
筋筋膜性疼痛症候群(myofascial pain syndrome)の痛みは1つの領域に限局している。
圧迫が痛みを生じる圧痛点(トリガー点)がある。
このときの痛みは、遠隔部に拡がり、患者が訴えていた痛みに似ている。
トリガー点の下に、ピーンと張った筋肉の帯を触れる。
この帯にある筋肉を伸展したり、この帯に局所麻酔を注入したり、針を刺したりすると、痛みは緩和する。
患者はトリガー点やピーンと張った帯のある筋肉を動かせないかもしれない。
あるいは、その筋肉を動かせば痛みが誘発される。
痛みが6ヶ月あるいはそれ以上続くと、予後がだんだん悪くなる。
圧痛点の局所治療は一時的緩和を生じるが、圧痛は戻ってくる。
多くの医師たちは、局所の原因がない局所性の痛みはありえないと思い込んでいる。
したがって、局所性の原因を証明できないので病気は存在しないと結論する。
疼痛学序説 筋筋膜性疼痛症候群より
その② 末梢神経の手術
除痛のために行う最も大きい手術は、椎間板ヘルニア除去術である。
一部の外科医たちは、椎骨の動きを制限するための骨移植を同時に行なっている。
椎間板ヘルニアの手術は70年以上もの間行われてきた。
もてはやされたこともあったが、疑問が増し続けている。
ヘルニアの突出と痛みはそれぞれ独立していて、痛みの発現における突出の役割ははっきりしない。
以前、この手術を熱烈に支持していたマイアミ大学は、今ではこの手術をやめて、厳密なリハビリテーションのプログラムを採用している。
またもや、手術が有効なのは、暗示によるものか、それとも痛みの明かな発生源部位組織の何か得意的な撹乱によるものか、全くはっきりしていない。
疼痛学序説 末梢神経の手術より
トリガーポイントの発生から痛みが慢性化するしくみ
【 トリガーポイントの発生 】
筋膜のトラブルが発生すると、その領域の血液の流れが阻害され『酸素欠乏』になります。
酸素欠乏が起きると、血液中の血漿から『ブラジキニン』などの発痛物質が生成され、知覚神経(C線維)の先端にある『ポリモーダル受容器』に取り込まれて『痛み』を感じます。
このような状態から発生した圧痛点(痛みの発信源)を『トリガーポイント』と呼びます。
【 痛みの慢性化(悪循環)】
『トリガーポイント』からの痛み信号を捉えた『脳と脊髄』が、反射的に交感神経を働かせます。
その結果、トリガーポイント周辺の『筋肉と血管の収縮』が起こり、再び酸素欠乏が発生して発痛物質が生成されるという『痛みの慢性化(悪循環)』が起こります。
心の痛みは本当に痛む
痛みとネガティブな感情は、深く絡み合っています。
私たちは、悲しいことや辛いこと(家族や仲間や恋人からの拒絶、別れなど)があった時、『心が痛む(傷ついた・折れた)』などと表現します。
近年、脳内の活動をオンライン(f MRI)で解析することができるようになり、痛みと感情の関係(身体的な痛みと心の痛みのつながり)が明らかになりました。
たとえば、人間関係で人に拒絶された時に傷つきやすい人は、身体的な痛みについても 強く不快と評価する傾向がある そうです。
また、たとえ傷つきやすくない人でも、社会的な苦悩(人間関係の中で苦しみ悩むこと)を経験をすると、身体的な痛みに対する 不快な知覚が増す そうです。
説得力のある事実として、人間関係における拒絶(ゲームのメンバーから外されるといった軽度な排斥でも)と身体的な痛みとは、脳の中の同じ領域 が活性化します。
もっと強力な拒絶を用いた研究では、恋人と別れたばかりの人に元恋人の写真を見せると、脳の中の感情的な痛み領域だけでなく、感覚的な痛み領域も活性化することがわかりました。
Social rejection shares somatosensory representations with physical pain
『社会的拒絶は、身体的な痛みと体性感覚を共有する』
この研究は、2011年にミシガン大学がおこなったもので、NHKのヒューマニエンスという番組「"痛み"それは心の起源」でも紹介されていました。
『心が痛む(傷ついた・折れた)』といった表現は、単なる言葉のあやではなく、現実的な比喩だったのです。
脳にとって『心の痛み』は『身体の痛み』と同じものなのです。