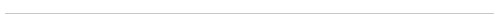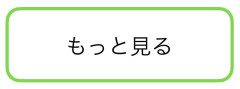そよ風 note
痛みやしびれを感じるしくみ
痛みやしびれを感じる部位や程度は人によって異なりますが、そのしくみは『みな同じ』です。
慢性的な痛みやしびれでお困りの方が、ご自身にとって『最適な治療や施術を受ける』ためにはそのしくみを知ることがとても大切です。
慢性痛が国際疼痛学会で定義され、『痛みの生理学』は飛躍的に発展しました。
慢性痛の研究が進むにつれて『痛みを知る(正しく理解する)』と『痛みをコントロールできるようになる』ことがわかってきました。
ところが。
『痛みを誤って理解している(させられている)』と『痛みの慢性化(痛みの悪循環)に拍車がかかる』こともわかりました。
『痛みを知る』ということは『痛み治療の一つ』でもあり、ヘルスリテラシーを高めて大切な『身体とお金を守る』ことができるようになります。
『痛みやしびれを感じるしくみ』が、いつまでも どこへ行ってもよくならない慢性的な痛みやしびれでお困りの方の一助となれば幸いです。
腰痛と画像検査
近年、『椎間板ヘルニア(頚椎および腰椎)』『脊柱管狭窄症』『分離症やすべり症』『変形性脊椎症』などの 構造的な異常が、痛みやしびれなどの症状とは必ずしも直結しない(直ちに症状と結びつけることはできない)ことが明らかになってきました。
例えば、MRIで椎間板ヘルニアが見つかっても、まったく無症状の人がいる一方で、強い痛みを訴える人もいます。
この事実は、「画像上の異常 = 痛みの原因」とは一概に言えないことを示しています。
しかし現在でも、レントゲンやMRIの画像で見つかった構造的な異常を、そのまま症状の原因と捉える傾向が強く残っています。
その背景には『構造的な異常(元の状態には戻らない変化)が、痛みやしびれの原因です』と説明したほうが、慢性的な症状が思うように改善がみられない場合でも納得しやすいことが挙げられます。また、治療(手術)や通院に対する患者さんの理解や同意を得やすいこともあるでしょう。
以下では、整形外科やペインクリニックの先生方の著書から一部を引用し、その内容にあわせて(私と私が施術した患者さんの)画像を供覧しています。ぜひ、参考にしてください。
みなさまからいただいたお声
頭痛持ちというのは・・・(30代 女性)
もう解決しない問題だと思っていました。
睡眠中に頭痛で目が覚めることも珍しくなく、このような体質と向き合っていくしないとも諦めていました。
先生の微振動治療と出逢い、体質改善されていく感覚を初めて知りました。
カウンセリングの時間も設けてくださるので、どんな症状に悩んでいるのかしっかり聞いていただけるのも安心できました。
今まで受けてきた治療とは根本的に違い、心も身体もとてもリラックスした状態で施術を受けることができます。
施術が終わると身体は軽く、体温も少し上がる気がします。
治療に通えない期間が長くなると、身体全体が強張り頭痛も酷くなることに気が付きました。
私の場合は慢性的に痛む期間が長かったので、自分に合ったペースで定期的に施術を受けることで身体をいいバランスで保ちながら生活できることがわかりました。
日頃頑張っている身体にご褒美として先生の施術を受けている感覚です。
首の痛みに始まり背中の張り・・・(50代 女性)
頭の中まで引きつられる感覚に襲われ駆け込んだ “施術室しまだ”
温かな雰囲気の室内・先生の穏やかなお人柄でリラックスして施術を受けることができました。
身体全体が例えるなら ”アロンアルファの付いた指”でツレている感覚が全身にあり、身の置き場もない程辛い状態でした。
思う様に身体が動かせず、ベッドに横たわる事ですら辛かったのですが、施術を受けた夜には可動域も広がり痛みも落ちついており、 久しぶりに当たり前に身体が動かせる事ができ嬉しかったです。
先生より筋膜のお話をしていただき、私の様に身体の造りを知らない素人にも筋膜を鶏肉の白い膜で丁寧にご説明いただきました。
歳だからと諦めずに”施術室しまだ”のドアをたたき、先生にお会いできて感謝しております。
先生と出会い、数回通わせていただいていますが・・・(40代 女性)
色々な事が勉強になり、また体調も凄く良いです。
右足首靭帯損傷の過去があり、疲れが溜まり鈍痛などもありましたが、先生に筋膜調整をしていただき、次の日には脚も軽く違和感もなく走る事も出来ます。
その技術には、驚かされます。健康に気遣い日々を過ごしていますが、これからもお世話になる予定です。
筋膜の大切さ、本当に身体からで実感。これからも宜しくお願い致します。
坐骨神経痛の成りすまし
トリガーポイントが形成されると、痛み、しびれ、関節の動きの制限などの『関連症状』が現れてきます。
よくある関連症状としては、臀部(お尻)の『小臀筋(しょうでんきん)』にトリガーポイントが形成されると『坐骨神経痛と誤診される痛みやしびれ』が脚に現れてきます。(本当に多いです)
海外では 坐骨神経痛の成りすまし として『偉大なる詐欺師の筋肉』とも呼ばれています。
ですが、小臀筋からしてみれば、自分の領域にトリガーポイントが形成されたから関連症状(坐骨神経痛と誤診される痛みやしびれ)を脚に現しているだけで(坐骨神経痛に成りすますつもりなどないはずですが)、トリガーポイントを知らない多くの医師が『この症状は坐骨神経痛(神経の圧迫による痛みやしびれ)だ』と判断するので『誤診の第一位は坐骨神経痛』になるのです。
でも、もし本当に神経が圧迫されてしまったら『麻痺(刺激が電気信号に変換されなくなる)』は起こっても『痛みやしびれ(刺激が電気信号に変換される)』は起こらないはずなので、坐骨神経からしても迷惑な話だと思います。
ちなみにですが、椎間板ヘルニアが神経を圧迫すると坐骨神経痛が引き起こされると考えられたのは、1911年(明治44年)です。
また、小臀筋のトリガーポイント以外のよくある関連症状として、首の『胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)』に形成されたトリガーポイントから生じる頭痛、肩こり、めまい や 頭や頬にある『咀嚼筋群(そしゃくきんぐん:噛むときに働く筋肉たち)』に形成されたトリガーポイントから生じる顎関節症、頭痛、耳鳴り などがあります。
最初のトリガーポイント『キートリガーポイント』に対して適切なケアを受けられないでいると、そのトリガーポイントがきっかけとなって、二次的に新たなトリガーポイント『サテライト(キートリガーポイントから離れたところにある)トリガーポイント』が形成されて新たな症状が現れてきます。
女性の筋膜に対するホルモンの影響
これまで、肩こりや腰痛や関節痛など(筋骨格系の痛み)の有病率は、男性よりも女性の方が有意に高く、女性の方が慢性化しやすいことは知られていましたが、その理由はよくわかっていませんでした。
ところが、筋膜の研究が進むにつれて、ホルモンが女性の筋膜に及ぼす(女性患者さんを治療するうえでの)重要性が明らかになってきました。
女性の筋膜を調べた研究では、女性の筋膜の細胞には性ホルモン受容体(ホルモンと作用するタンパク質:細胞に情報を伝えるもの)が含まれていて、閉経後の女性では閉経前の女性に比べて受容体の発現量が少ないことがわかりました。
現在では、更年期(40歳〜55歳くらい)から閉経後において、ホルモンバランスが変化するにつれてコラーゲンとエラスチンの比率が変化し、筋膜の組織とその働きに変化を引き起こすことがわかっています。
『コラーゲンとエラスチンについて』
筋膜は、コラーゲンとエラスチンと水分でできていますが、ホルモンの影響を受けるのは主にコラーゲンのようです。
コラーゲンという名前は「接着剤」を意味するギリシャ語の「kólla」 と「生成」を意味する接尾辞の「gen」 に由来します.
現在、コラーゲンには19種類の型があり、Ⅰ 型、Ⅱ 型、Ⅲ 型、・・・と分類されています。
その中でも Ⅰ 型コラーゲンは身体でもっとも多く、皮膚、骨、腱、靭帯、筋膜にあり、全コラーゲンの90%を占ます。
そして、Ⅰ 型コラーゲンは鉄鋼よりも強く、強大な張力に耐えることができるほどとても頑丈なので、筋膜は「第2の骨格」と言われています。
Ⅱ 型コラーゲンは、Ⅰ 型コラーゲンよりもずっと細く、軟骨と椎間板にあります。
Ⅰ 型 と Ⅱ 型のコラーゲンは張力に抵抗しますが、伸張できるのは元の長さの10%までです。
Ⅲ 型コラーゲンは、皮膚、骨膜、(平滑)筋、動脈、内臓などにあり、柔軟な臓器の構造を維持し、創傷(きず)を治し、腱・靭帯・骨膜が骨に付着する部分として機能しています。
エラスチン線維は、コラーゲン線維よりも細く、反発力を加える弾性線維(組織がゴムのように伸縮する柔軟性)です。
コラーゲンとエラスチンは互いに交差したり螺旋状に巻き付いたりして、強度と弾力性を与えています。
エラスチンは元の長さの230%まで伸張しますが、その機能は、加齢や太陽の光によって低下してしまいます。
『エストロゲンと筋膜』
エストロゲン(卵胞ホルモン):妊娠の準備をするホルモン
・子宮内膜を厚くして妊娠に備える
・女性らしい身体をつくる
・自律神経の働きを安定させる
・Ⅰ 型コラーゲンの産生を促す
・血管、骨、関節、脳などを健康に保つ
エストロゲンは、Ⅰ 型コラーゲンの産生を促し、コラーゲンの架橋(コラーゲンの安定維持のために結びつく)濃度を高め、Ⅲ 型コラーゲンを減少させることによって、筋肉と筋膜を強化します。
また、コラーゲンとエラスチンの分解を遅らせて、筋膜が硬くなること(弾力性や伸縮性の低下)から保護しています。
したがって、閉経期移行中および閉経後にエストロゲンのレベルが低下すると、筋膜は硬くなって、弾力性や伸縮性が低下してしまうのです。
『プロゲストロンと筋膜』
プロゲストロン(黄体ホルモン):妊娠を維持するホルモン
・エストロゲンの働きによって厚くなった子宮内膜を柔らかく維持して妊娠しやすい状態にする
・水分や栄養をため込み、妊娠を維持する
・体温を上げたり、食欲を増やしたりする
ホルモンが筋膜に影響を及ぼす一つの重要な領域は、食道と胃の境目にある「下部食道括約筋」です。
下部食道括約筋は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流しないように、胃の噴門(胃の入り口)を締める働きをしています。
妊娠中のエストロゲンとプロゲストロンの上昇は、下部食道括約筋の締まりを緩ませるので、妊娠中に高頻度にみられる胃食道逆流症の病因となります。
『筋膜性の痛み(筋膜性疼痛症候群)』
筋膜性の痛みには、年齢との間に相関関係があることがわかりました。
ある研究では、高齢の人は若い人よりも側頭部(頭)の筋膜が硬いことを示しています。
年齢が上がるにつれて、より硬く柔軟性の低い筋膜が形成され、滑走性(組織が互いにすべり合う動き)が低下します。
痛みの原因となる筋膜にそのような変化が起こると、筋膜性疼痛症候群(痛みや関節の動きの制限)を引き起こします。
筋膜性疼痛は、男性よりも女性に多く、閉経前の女性よりも閉経後の女性に多い。
参考にした本「Fascia, Function, and Medical Applications(筋膜、機能、医療への応用)」には、以下のことも書いてありました。
・筋膜と痛みの関係が明らかになったことで、医師は、単に症状を緩和するために薬を処方するのではなく、筋膜を慢性的な痛みの病因として考慮しなければいけない。
・ホルモンが筋膜組織にどのような調節不全を引き起こすかについての知識は、筋膜性疼痛の性差の違いを理解し、女性患者さんを治療する際にはとても重要である。
・これまでの研究によって、ホルモンが女性の筋膜の健全な機能をサポートするうえで重要な役割を担っていることがわかった。臨床家(医師や治療家)は、女性患者さんを治療する際に、このことを念頭におくべきである。
・ホルモンが筋膜組織にどのような影響を及ぼすかについての理解は始まったばかりだが、ホルモンが筋膜組織に影響を及ぼすことは明らかである。
これからも筋骨格系の痛みに対して、「背骨や椎間板の変形」「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「神経の圧迫」「関節の変形」「軟骨のすり減り」など、今まで通りの説明(治療)がされるなら、慢性化しやすい女性はより慢性化してしまいます。
そして「先進国中でもっとも遅れている」とされる日本の慢性痛医療は、もっとも遅れたままです。
症状が出ている期間が長い(数ヶ月から数年)ほど、トリガーポイントの数も多く、広範囲に及ぶ傾向があります。
◻︎参考文献◻︎
・「Fascia, Function, and Medical Applications (筋膜、機能、医療への応用)第2版」 2025
13章 Hormonal Effects on Fascia in Women(女性の筋膜に対するホルモンの影響)
・「ファシア ー その存在と知られざる役割 ー」医道の日本社 2020